はじめに|感情だけでは、移住先は選べない
前回の記事では、「自然の中で子育てしたい。でも、それだけでは決められなかった理由」というテーマで、 私たちが“自然への憧れ”と“現実の壁”のあいだで悩んできたことを書きました。
自然に囲まれた暮らしには強く惹かれるけれど、 それだけで場所を選んでしまうのは少し違う。 「本当に大切にしたい暮らしの価値観は何なのか?」を、私たちなりに深掘りした内容でした。
あの記事を通して私たち自身も気づいたのが、
「感情ではなく、“条件”として言語化することの大切さ」です。
この記事では、そんな気づきをもとに整理した、 “私たちが移住に求める6つの条件”を紹介します。
これは、誰かの正解ではなく、私たち夫婦にとっての“納得軸”。 これから移住を考えるすべての人にとって、自分なりの判断基準を持つヒントになれば嬉しいです。
条件①|“子育て”と“将来”に欠かせない、医療アクセスの安心
正直、移住を考えはじめた当初、私たちは「医療アクセス」をそこまで重視していませんでした。
それくらい、東京の暮らしでは医療の存在が“空気のように当たり前”だったからです。
「近くに小児科があるのは普通」
「夜間診療も、予約アプリですぐ取れる」
「セカンドオピニオンや専門科も迷わず選べる」
でも、地方の候補地をいくつか調べるうちに気づきました。
「医療を“選べる”こと自体が贅沢だったんだ」と。
特に子育て期や高齢期を見据えると、こんなことが現実的に起こります。
- 夜間の高熱 → 最寄りは救急外来なし、隣町まで40分
- 出産できる病院は市内に1〜2ヶ所のみ
- 予防接種や乳児健診が“月に1回しか枠がない”
- 高齢親の通院付き添いも“家族の負担が必須”
こうした環境に直面したとき、「病院があるか」ではなく「どう通えるか」が本質だと痛感しました。
自治体の移住相談では「自然環境」「空き家支援」「子育て制度」は教えてくれても、
地域の医療体制や住民の使い方までは、ほとんど触れられません。
だからこそ、意識して調べておかないと“見落とすリスク”が高いのです。
私たちが重視した、医療まわりの3つの判断軸
- 通いやすい距離(車で20〜30分以内)に小児科・総合病院があるか
- 地域で救急・夜間対応がどう機能しているか(←実は地域差が大きい)
- 「医療へのアクセス」は“将来の介護”にも直結すること
どうやって調べる? 私たちが実際にやった医療リサーチ
- Googleマップで「◯◯市 小児科 総合病院」などを検索し、距離と数をチェック
- 市役所や地域包括支援センターに電話して、医療体制や夜間対応について質問
- 地域の移住経験者のブログやSNSで、子育て中の医療事情をリサーチ
- 子育て支援NPOやママ・パパ向けの地域コミュニティを調べて、評判を確認
- 現地見学や移住体験住宅を使い、実際の通院シミュレーションをしてみる
こうした情報は、移住フェアやパンフレットには載っていないことがほとんどです。 だからこそ、自分たちで動いて調べることが、後悔しない判断につながります。
「自然があればそれでいい」は、理想のスタートライン。
でもその先には、“暮らしを成立させる”現実の条件があります。
条件②|“自然に囲まれたい”だけじゃない。「ちょうどよさ」のバランス感覚
「自然の中で暮らしたい」という気持ちは、私たち夫婦にとって移住の原点でもありました。
でも、実際にエリアを探し始めると気づいたんです。
“自然が多い=理想の土地”ではない、ということに。
私たちは東京の利便性の中で暮らしてきました。
日常生活に困ることはなく、移動も仕事も、買い物も医療も、すべてがコンパクトにまとまっています。
その中で得たのは、“便利さ”だけではなく、
「余計なストレスなく暮らせる安心」だったと気づいたのです。
完全な山間部や過疎地のように、「車がないと日常が成立しない」「買い物は週1まとめ買い」 ──そんな環境では、地方の自然と引き換えに新たな負荷が生まれてしまう。
一方で、自然と都市の両方の良さを持った“中間地点”のようなエリアも存在します。
- 地方都市の郊外で、駅・病院・スーパーが15分圏内にある
- ちょっと足を伸ばせば川や山があり、週末は自然とふれあえる
- 子どもが自然に触れつつも、教育や習い事の選択肢もそこそこある
そうした場所こそ、「日常の安定」と「理想の暮らし」が両立できる場所だと考えるようになりました。
私たちが求める“自然のある暮らし”とは、
ただ森に囲まれることではなく、「日常に無理なく自然を取り入れられる」バランスです。
私たちが見つけた「自然×都市のちょうどよさ」を測る3つの視点
- 徒歩・自転車・車移動のバランスが日常的に無理ないか
- 自然がある=「遊ぶ余白」が暮らしの中にちゃんとあるか
- 都市へのアクセス(新幹線/高速道路/特急)も、ある程度見ておく
自然の中でゆったりとした時間を過ごしたい。
でも、それがストレスや不自由の上に成り立つものでは意味がありません。
「自然が多すぎること」による不自由にもちゃんと目を向けながら、 私たちは「ちょうどよい」バランスを求めるようになりました。
地方移住は、“ゼロ or イチ”ではなく、
「都市と自然のグラデーションの中から、自分たちの最適解を見つける旅」なのかもしれません。
条件③|“フルリモート勤務”を支える、通信・ITインフラの安定性
地方に移住したいと思ったとき、真っ先に私たちが意識したのが「仕事の持ち運び」でした。
夫婦ともにフルリモート勤務という働き方を実現できたのは、 まぎれもなく都市部の安定した通信インフラと、仕事環境があったからです。
地方でも同じ働き方を続けるには、 “家の中が快適なオフィスになっていること”が絶対条件になります。
でも、想像以上にインフラ格差はある
地方といっても、すべてが同じではありません。
回線が通っていても「光回線が遅い」「安定しない」「そもそも選べる事業者が少ない」など、 “都市なら当然”のレベルに届かないケースも多くあるようです。
動画会議やオンラインツールを日常的に使う私たちにとって、 ・通信速度(下り上りともに100Mbps以上)
・時間帯による品質のばらつき
・回線の種類やプロバイダの選択肢 などは、今後の移住検討で最も重要な確認項目になっています。
まだ情報収集中の段階ですが、これから下記のような点を重点的に調べていく予定です。
今後チェックしようと考えている項目
- エリアごとの光回線対応状況(NURO/auひかり/ドコモ光など)
- 実際に住んでいる人のネット速度レビューや掲示板の評判
- 不動産サイトや移住紹介ページで、通信環境の記載があるか
- 現地に行くタイミングがあれば、スマホ・PCの回線テストも検討
こうしたITインフラは、見落としがちですが「仕事の継続」と直結しています。
今後、私たち自身がこのあたりを丁寧に調べ、また記事でも発信していきたいと思っています。
「自然に囲まれて働く」という理想を、ちゃんと機能する現実に変えるために。
移住候補地を選ぶときは、「ZoomやSlackが普通に使えるか?」という視点から見ていく予定です。
条件④|“どこで育てるか”より、“どう育てられるか”──教育の選択肢
移住を考えたとき、想像以上に悩んだのが「子どもの教育」についてでした。
「自然の中でのびのび育てたい」──これは本心です。
でも、教育の選択肢が限られていたらどうする?と考えたとき、 一気に不安が湧き上がってきました。
私たち自身、都市部で育ち、私立・公立・塾・受験・習い事… さまざまな選択肢に囲まれて生きてきました。 その結果として“今の仕事や思考力”があるとしたら、 やはり「選べる環境」は大切にしたいと感じたのです。
地方だと、選択肢が“そもそも存在しない”ことも
たとえば──
- 公立中学校が1校しかなく、学力や雰囲気を比較できない
- 塾や習い事の数が少なく、距離も遠い
- 不登校や学び直しに対応したフリースクールがない
もちろん、すべてが不利とは限りません。
地域によってはICT教育が進んでいたり、少人数制で先生との距離が近かったり、 都市部にはない良さもたくさんあります。
でもやっぱり、「選択肢の存在そのもの」があるかどうかは、私たちにとって重要な軸でした。
“何を選ぶか”は子どもが決める。でも“何を選べるか”は親が用意する。
これは、ある教育関係者の言葉で強く印象に残っているフレーズです。
私たち夫婦も、これにはとても共感しています。
子どもがどんな道を選ぶかはわからないけれど、
「こういう進み方もあるよ」という選択肢を見せてあげられる地域にいたい。 それが、私たちが考える“教育環境の豊かさ”です。
私たちが今後調べていく教育周りのチェックポイント
- 公立/私立の学校数とその特色
- 子どもが増えている地域か?(教育熱や施策の注力度)
- 図書館、学習センターなどの自習空間の充実度
- フリースクールや家庭教育支援があるかどうか
- 習い事・音楽・スポーツなど文化活動の選択肢
まだ子どもが生まれていない今だからこそ、
「環境を先に選ぶ」という視点を持っておきたい。 それが、地方移住を検討する今の私たちのスタンスです。
条件⑤|“地域に溶け込む”ではなく、“関係性を自分で設計する”という視点
移住について話すとき、必ず出てくるのが「地域との関係性」。
でも私たちは今、こう考えています。
「移住=地域に溶け込まなきゃいけない」ではない。
むしろ「自分たちが心地よく関われる関係性を、自分たちでデザインしていく」ものだと。
これは、夫である私が地方創生の現場でずっと感じてきたことでもあります。
どれだけ“移住者ウェルカム”な地域でも、「関わり方のバリエーション」がないと、 住む人も受け入れる人もしんどくなってしまうからです。
“村社会が嫌だ”と一括りにする前に、地域には多層なコミュニティがある
たとえば一つの地域の中でも──
- 伝統的な自治会・町内会
- 地域おこし協力隊や移住者サークル
- 教育系NPOや子育て支援団体
- SNS経由でつながるオープンな人たち
地域には、さまざまな“関わり方の窓口”があります。
どこを選ぶか、どこに寄るかは自分たちで設計できるというのが、私たちが感じているリアルです。
移住してから関わるのではなく、「移住前から関われる」時代
今はSNSやブログで「誰がどんな活動をしているか」が見える時代。
その中で、“移住者になる前に、地域に関わる人”になることもできるようになりました。
たとえば、
- Twitterで地域の起業家や団体の発信をフォローしておく
- 地域に関心があることを発信し、共通点のある人とつながる
- 現地に行かなくても「話せる・調べられる・交流できる」環境をつくる
私たちも今、ローカルリビングというメディアを通じて、 “まだ移住していない私たち”の視点で地域との関わりを模索しています。
私たちが今後調べていきたいこと
- 地域に多様な関わり方(緩やか/深い/一時的)が存在するか
- 移住者の活動事例やブログ/SNS発信が盛んか
- 地域に“余白”があるかどうか(何でも参加しろ!の空気じゃないか)
「馴染めるか?」より、「どう関わりたいか?」を起点に選ぶこと。
それが、私たちが考える“これからのコミュニティの距離感”です。
条件⑥|自分たちらしく、納得感のある働き方を“続けられるか”
「地方に住みたい」と思ったときに、私たちが一番慎重になったのが、
「働き方を犠牲にしないか?」という点でした。
どんなに自然が豊かでも、家賃が安くても── 自分らしく働き続けられなければ、意味がない。 そう思った私たちは、移住前にまず“仕事のあり方”を整えることから始めました。
「自分らしい働き方」とは何か?
単にリモートワークができる会社に入ればOK、ではありません。
大切なのは、その働き方のなかで自分の価値が発揮できるか、 評価され、やりがいを持てるか、そして家族の暮らしと両立できるかです。
私たちが求めていたのは、「地方で“生活の豊かさ”を感じながら、
キャリアの面でも納得感を持ち続けられる働き方」でした。
移住前に“働く基盤”をつくっておく理由
- 地方に移ってから仕事を探すのは難易度が高い
- 移動や環境変化で生活コストが一時的に増えることもある
- 育児や引越しとの並行で、新たな就職活動をする余裕がない
だからこそ、都市にいる間に「場所を問わず働ける実績とスキル」を積んでおく。
この戦略が、私たちにとっての“移住の土台”になっています。
「今の仕事を持って、場所だけを変える」という発想
これが、いわゆる“持ち運べるキャリア”です。
場所を変えても、仕事の本質や成果は変わらない。 そんな土台を築くことができれば、 住む場所も、暮らし方も、自分で選べるようになると実感しています。
今後の働き方の条件として、私たちが重視していること
- フルリモートや柔軟な働き方が、制度として定着している
- 評価基準が「出社前提」ではなく、成果主義である
- 都市部と同じように、成長機会や新しい挑戦がある
- 家庭との両立を前提とした業務設計が可能
働くことは、暮らすことと地続きです。
「地方だから仕方ない」と、働く納得感をあきらめない。 これが、私たち夫婦のこだわりです。
さいごに|“選ぶ前に、考えた”からこそ、後悔しない選択へ
ここまでご紹介したのは、私たちが実際に移住を検討する中で、
本気で向き合った6つの条件です。
- ① 医療へのアクセス
- ② 自然と都市のバランス
- ③ 通信インフラと仕事環境
- ④ 教育の選択肢
- ⑤ 地域との距離感
- ⑥ 働き方の持続可能性
どれも「当たり前」のように見えて、住んでからでは取り返しがつかないことばかり。
だからこそ、移住を“直感”ではなく、“設計”として考えたい。 それが私たち「ちい夫婦」の想いです。
選択肢が多いようで、実は少ない。だからこそ「自分で選ぶ力」を持ちたい。
特に、これから生まれてくる子どもには、
「当たり前のルート」ではなく、自分で選択し、切り拓ける人生を歩んでほしい。
そのためにも、まずは私たち自身が、“選んだ暮らし”を体現していきたいと思っています。
次回予告|じゃあ、どの地域が良いのか?
次回の記事では、今回の6つの条件をもとに── 「実際に気になっている地域」「どう候補地を絞り込んでいるか」についてお届けします。
私たちがどう比較し、どんなポイントで選ぼうとしているのか?
リアルな検討プロセスをそのまま綴っていく予定ですので、ぜひご期待ください。
▶️ 次の記事:「私たちが本気で移住を検討している地域リスト」(近日公開予定)
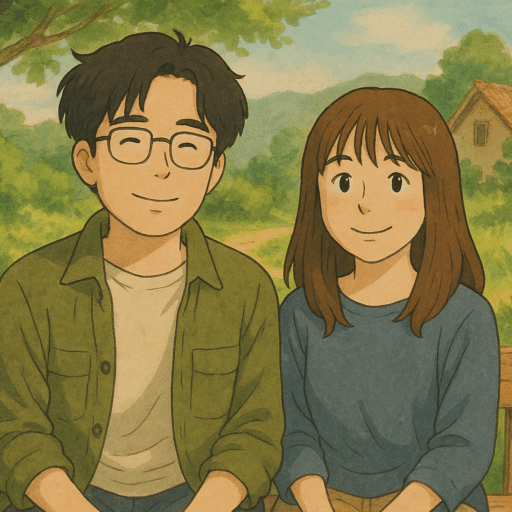



コメント